33 森地域の戦争体制と人々
1931年(昭和6年)9月18日、満州事変が勃発し、1937年(昭和12年)7月7日の盧溝橋(ろこうきょう)事件、1941年(昭和16年)12月8日真珠湾攻撃から原爆投下におわる約15年間のアジア太平洋戦争の間、森町地域の人々も否応なしに戦争体制に巻き込まれていった。
その直前までの自由な雰囲気の教育もかき消え、政党政治も解体し、軍部主導の戦時経済化も急ピッチで進行した。日常生活面では米の配給、物資供給の調整と物価統制が進む中で、人々の暮らしでは、ますます物々交換と闇の買い出しがその生活防衛策となっていった。戦争一色に塗り込められた戦地への動員と森町高等女学校、周智農林学校生徒の勤労動員、地下工場設営のための朝鮮人流入も隣の原谷村だけではなく、森町地域にも及んだ。 軍事動員を余儀なくされた若い男子は、中国戦線の地で、またフィリピンでアメリカ軍との白兵戦で、あるいは戦争に出かける艦船の中で、航空機による爆撃のために犠牲となり、また戦後シベリアに抑留(よくりゅう)されて過酷な労働の中で命を失った。さらに兵士ではないが、問詰など貧しい山村地区などからも、高等小学校を卒えたばかりの16歳前後から19才までの満蒙(まんもう)開拓青少年義勇軍が組織されていった。
1940年(昭和15年)6月1日、森町地域の人々にとっての長年の悲願であった国鉄二俣線の都田−遠江森間が開通し、掛川−新所原間の全通を見た。これは森町から奥地の山間部の物資を国鉄網に直結させるという画期的な意義を持つものだった。
(1)「大東亜共栄圏絵図」

(森町教育委員会所蔵)
(2)入営記念写真

(森町教育委員会所蔵写真)
(3)軍服などの遺品

町民の方から森町歴史民族資料館へ寄贈いただいた戦時下の遺品。 「大日本国防婦人会」のタスキは、白い割烹前掛けの上に右肩から斜めに掛けた。婦人は各村ごとに分会組織を結成して、このタスキを掛けた記念写真を撮り、はがきに印刷して戦地にいる夫や息子の安全を祈って郵送した。(森町歴史民族資料館所蔵)
(4)軍人送迎参加票

(西俣町内会所蔵)
(5) 銃剣(じゅうけん)の訓練

(森町教育委員会所蔵写真)
(6)金物の供出(きょうしゅつ)

(森町教育委員会所蔵写真)
(7)本土決戦弾薬貯蔵穴

(森町一宮 片瀬大ガケ)
| 死亡時期 | 死亡人員 |
|---|---|
| 1935年 | 1 |
| 1936年 | 0 |
| 1937年 | 2 |
| 1938年 | 3 |
| 1939年 | 4 |
| 1940年 | 2 |
| 1941年1月~12月7日 | 7 |
| 1941年1月28日~12月31日 | 0 |
| 1942年 | 13 |
| 1943年 | 21 |
| 1944年 | 87 |
| 1945年1月~8月14日 | 66 |
| 1945年8月15日~12月31日 | 20 |
| 1946年1月~12月31日 | 9 |
| 1947年 | 2 |
| 1948年 | 3 |
| 1951年 | 1 |
| 不明 | 3 |
| 合計 | 244 |
| 階級 | 戦没人員 |
|---|---|
| 二等兵 | 5 |
| 一等兵 | 17 |
| 上等兵 | 36 |
| 兵長 | 62 |
| 伍長 | 74 |
| 軍曹 | 11 |
| 曹長 | 9 |
| 准尉 | 0 |
| 少尉 | 2 |
| 中尉 | 1 |
| 大尉 | 5 |
| 少佐 | 1 |
| 中佐 | 0 |
| 大佐 | 0 |
| 海軍水兵 | 1 |
| 三等兵曹 | 2 |
| 以上 | 226 |
| 義勇軍 | 1 |
| 軍属 | 20 |
| 合計 | 247 |
| 森町人口 | 数 | 戦死比率 |
|---|---|---|
| 全体 | 7,172人 | 3.5% |
| 推定男子 | 3,471人 | 7.2% |
| 推定世帯数 | 1,464戸 | 17.1% |
| 森町人口 | 数 |
|---|---|
| 全体 | 10,367人 |
| 男 | 5,019人 |
| 女 | 5,348人 |
| 男性比率 | 48.4% |
| 世帯数 | 2,109戸 |
| 1世帯人員 | 4.9人 |
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






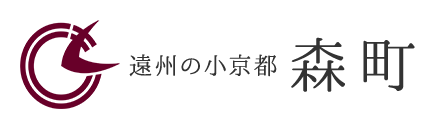

更新日:2019年03月05日