34 戦後発展と21世紀の森町へ
戦後は、敗戦を告げる玉音(ぎょくおん)放送とともに始まった。しかし森町のような、空襲を免れた地域では、人々にとっての戦争後の状態はなんといっても、比較的安定していたと実感されているかも知れない。もっとも1944年(昭和19年)12月7日昼過ぎの東南海地震による南部地域を中心とした家屋の倒壊などの被害は決して忘れ去ることのない戦時下の災害であった。
農地改革後の森町は、一部では綿工業への着手もあったが、それ以上に、米作を始めとする農業生産が戦後復興の源泉にもなった。また、戦時中から始まった菜種の栽培による食用油製造も見られ、戦後の燃料として木炭の生産も重要であった。森町地域を始め静岡県の木炭の品質は全国的に見て、上位にあった。1950年代は概して農地改革後の農村が一気にその生産力を上げて、農政もまた食糧自給に重点を置いた。農山村住民にとって比較的安心できるものであったと言ってよいであろう。
1950年代に戦後復興を終えて、全国的な高度経済成長の段階に突入すると、エネルギー源が水力から石油へと大転換し、しかも家庭用燃料としても木炭などから灯油への転換が行われた。
森町のような山村部の林業家をかかえる地域では、経済的に低迷を始めていった。50年代後半から、1963年(昭和38年)に至る前後に森町は1町5か村による合併を遂げた。町部地域への人口集中、山村部の人口流出と過疎化を引き起こし、南部地域は農業地帯として生産力の高さを誇ったが、一方ではベッドタウンとしての役割も果たしつつあった。人口がこの地域に傾斜して増加したのである。
高度成長が第一次石油危機(1973年)でほぼ終わり、その後長期の低迷と1980年(昭和55年)代の一時的なバブル化を受けて、90年代のバブルの破錠と長期の停滞とは森町地域にも大きな負の遺産を残してきている。財政の逼迫(ひっぱく)、人口の過疎化、高齢化、進出企業の低迷と商工業の停滞、農林業の著しい後継者不足など、21世紀に向けて、山積した課題を積極的に打開する方策が、いま求められている。その際、地域の歴史的伝統を活かした、産業の振興、文化遺産の継承、自然環境の美しさを誇るべき私達の財産として大いに活用することが求められている。
(1)昭和28年の森町

「森町町勢要覧」に残された森山(三島山)付近の全景。
(森町役場商工観光課保管)
(2)現在の森町

三島神社の杜は「森」の語源となった山である。
(3)町村合併にかかわったみなさん

天方村・森町・飯田・園田・一宮は昭和30年、三倉と旧炭焼村は翌31年に森町となった。
(『森町むかしといま』より)
(4)合併決議謄本

(森町役場文書)
(5)森町立旭が丘中学校全景 (左:開校当時,右:現在)


旧校舎は1953年(昭和28年)宮園中学校として出発、飯田中学校と合併して旭が丘中学校になった。
(森町谷中)
(6)森町体験の里「アクティ森」

1991年(平成3年)5月部分竣工開業、1992年(同4年)4月レストランなど、1993年(同5年)4月農産物加工場ほかが開業する。
(森町問詰)
(7)森町役場庁舎

1965年(昭和40年)11月3日落成。 (森町森)
(8)森町文化会館

1995年(平成7年)3月竣工 (森町草ヶ谷)
(9)森町立森町病院

1997年(平成9年)3月竣工 (森町草ヶ谷)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






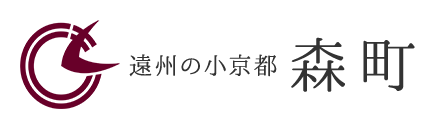

更新日:2019年03月05日