36 小國・天宮両社の舞楽
(1)天宮神社楽登り(がくのぼり)

場内には、旧神宮寺の建物が残っており、ここが現在も練習所である。
(天宮神社)
(2)凱生社社庫

天社穀(てんしゃこく)(若者衆)の人たちは、秋の三島神社祭にが屋台を巡向する。
(森町天宮)
(3)遠江の国見岳本宮山と一宮神領域

中央の山頂は小國神社の本宮奥岩戸神社祀られている社叢(しゃそう)。 手前の水田は一宮円田郷で、この右(東)に蓮華寺がある。
(4)太平楽

天宮神社の太平楽は、鳥兜(とりかぶと)のすそをつり上げてかぶる。 しかし、小國神社の場合はつり上げはしない。 このほか、鉾の扱いにも対をなす所作がみられる。
(天宮神社)
(5)菩薩(色香)

両手にさんじょうを持って渡廊を渡るところである。
大人二人舞で天宮菩薩の出現であろう。
(天宮神社)
(6)獅子

両社の獅子頭は阿吽(あうん)の対で、赤と青、角の有無などが明らかである。
(天宮神社)
(7)安摩

神の面を付けることから「かんめん」とも言われるもので、面の額部分が白の天宮と黒の小國は対の面である。
(天宮神社)
(8) 納曾利 ( なそり )

地に伏す所作の多い天宮の納曾利は青装束である。 (天宮神社)
(9) 浜垢離 ( はまごり )

舞ぞろい日の午前中におこなわれる塩井神社への参拝は潮くみの大切な行事である。
(小國神社末社塩井神社)
(10)花の舞

番外の曲で延舞の前に社家の人々によっておこなわれる清めの酒である。
(小國神社)
(11)菩薩(色香)

手をひし形にして左足を前に出したところである。
この手は、女性を意味し、次の所作では人差指を立てて男性を表現する。 これは、世の中が男女の交わりによって繁栄することを意味する。
(小國神社)
(12)庭胡蝶

稚児4人で舞うが、一、二の稚児は赤、三、四は青の上着である。 中央の舞楽では、胡蝶という。
(小國神社)
(13) 拔頭 ( ばとう )

稚児の一人舞ともいう。 伝承では、あまりの美しさにさらわれたので、以来、「ざっとろぼー」をしてもどきをするという。
(小國神社)
(14) 納蘇利 ( なそり )

天をあおぐように大きく舞い、赤装束を着ける。
(小國神社)
(15)二ノ舞

翁(おきな)と媼(おうな)の舞(もどき)で、安摩とは番舞(つがいまい)となっている。 神の舞である安摩を真似ようとするが上手にできない。 これが「二ノ舞を踏む」の語源である。
(小國神社)
(16)龍王

陵王(りょうおう)ともいう。 これも天宮では青い装束を着けて舞うが、小國は赤色で両社一対の相違をみせる。
(小國神社)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






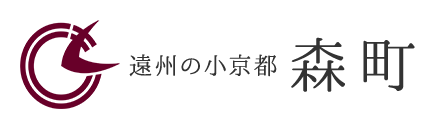

更新日:2019年03月05日