43 衣・食・住
自然とともに生きていたころは、着るもの、食べるもの、住むところなど生活のほとんどは手作りのものだった。
昭和10年代までは暖房も冷房もないのだから、暑いときは裏がついていない 単 ( ひとえ ) のもの、寒くなればネルの下着をつけて綿入れを着るという生活。破れれば縫い合わせ、 威 ( い ) がなくなれば当てこをして長く使ったから森のボロ市が栄えたということが理解できよう。
農作業には男は紺 襦袢 ( じゅばん ) に 股引 ( ももひき ) 、女はカスリの野良着に赤い腰巻き、手甲とハバキをつけてタスキを掛けた。戦時中からモンペが用いられるようになる。たまに晴れ着を着ると気分が高揚したのも当然である。
食事は日が長いころは4回食べた。6時の「おちゃのこ」、10時の「お茶助(ちゃすけ)」、2時の「おようじゃ」、夜の「オイハン」で、さらにヨーナビ(夜なべ仕事)をすると「オヤショク」をとって寝た。食べるものは麦飯が中心で、ソバやウドン、オハタキ(くず米の餅)などもよく食べた。おかずは自家用の野菜が中心であったから、モノ日(特別な日)や冠婚葬祭のご馳走は魅力的であった。おやつはサツマ芋が多かったが、柿や栗、山桃、グミ、ヤンゾウコンゾウ、桑の実、シイ、野イチゴなども食べた。
農家の屋敷は、マキ囲いをしてカラッ風を防ぎ、真ん中には母屋、西北にお蔵と地の神、東側に長屋と外便所(しもや)、井戸、薪小屋があり、南側は広いオードがあって農作業をする広場となっていた。母屋は合掌造りが多く、以前はカマヤ造りもあった。屋根はカヤ葺きや杉皮葺きがほとんどだった。
(1)のら着生活93年

竹島老翁は、9月の残暑のなかで大根の種蒔きをしていた。
(森町天宮 大上 平成10年9月)
(2) 野良着 ( のらぎ )

片吹で使われてきたものである。 袖も鯉口のものやさまざまである。 よく当てこがしてあって生活の様子がみえてくる。
(森町亀久保 片吹)
(3)婚礼打掛け

大正2年に用いたもので、お色直しに着用した。すそには小さな花模様のししゅうがあって、たいへんおしゃれなものである。
(森町 個人所蔵)
(4)婚礼の写真

小國神社において撮影
(5)葬儀の写真

庭(オード)でおこなった。 (森町一宮)
(6)ニワそうじ

92歳になっても家の中は年寄りの仕事だという鈴木さん。 礼儀正しい姿は美しい。
(森町中川上)
(7) 梅衣 ( うめころも )

明治初年に加藤むめによってつくられた梅衣は、小松宮殿下をはじめ天皇陛下もお買上げになられた。 お茶のさかんな森町は、お菓子屋も多い。
(8) 庚申 ( こうしん ) さまのご馳走

天宮大上の大当(おおとう)連中で行う。 60日に1回来る庚申さまの献立は、赤飯・みそ汁・ヒリューズ・煮豆で、お拝をしてからいただく。
(森町天宮 大上 平成10年9月5日夜)
(9)山ノ講のぼたもち

山の神様にお供えし手の平もある程のぼたもちを作ってお供えする。
(森町一宮)
(10)味噌部屋

つけものや味噌などを貯えておくところで、家の中や蔵のヒサシにあった。
(森町亀久保)
(11)十二の供餅

毎年正月にお供えする12個のヘソ餅で、「おてんとうさん」ともいう。
(森町中川下)
(12)こうじの製造

糀・麹・味噌・金山寺を作る店では、農家から注文された米に糀(花)を付けて届けたり、なっとうを漬け込んだりする。
(森町森 新町)
(13)梅の土用干し

6月に漬けた梅はシソを入れたのちに天日干しにして仕上げる。
(森町飯田)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






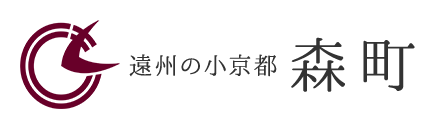

更新日:2019年03月05日