10 一宮の成立と密教の隆盛
小國神社は、周智郡内の官社で、その祭祀(さいし)や営繕(えいぜん)は、郡司(ぐんし)や国司(こくし)の支配による律令下に置かれてきた。
1082年(永保2年)、神祇官は太政官を通じて小國社の 神主職 ( かんぬししき ) に 清原則房 ( きよはらののりふさ ) を 補任 ( ぶにん ) し、翌永保3年には、遠江国司藤原 惟信 ( これのぶ ) が同氏を同社の 宮司職 ( ぐうじしき ) に補任した。
清原氏は、代々 小國 ( をくに ) 社(神領と領民)の実質的支配者で、散在していた 神田 ( じんでん ) を 国衙領 ( こくがりょう ) や他荘園を交えないで一円化( 円田化 ( えんでんか ) )し、小國社の経済基盤を確立した。清原氏は、円田用水(太田郷から引水)を整備し、広大な水田を開発したと見られる開発領主である。円田郷の 大城戸 ( おおきど ) は、清原氏の館と推定され、 深養父 ( ふかやぶ ) と別称されたが、その後「 粟倉殿 ( あわぐらどの ) 」と変ったようである。
清原氏は、遠江国へ赴任した国司藤原氏や都の権門盛家(けんもんせいけ)と結ぶことにより、この10年後には神官別当(しんかんべっとう)が従五位下を買官(ばいかん)している。また、1165年(永万元年)、小國社は遠江で唯一神祇官へ八丈絹5疋(ひき)を貢納する神社であった。
1168年(仁安3年)、小國社へ天台如法経(にょほうきょう)が埋納されたことは、蓮華寺(八形山(はっけいざん))や岩室寺(いわむろでら)が同社と融合した密教寺院であったことを推定させる。天宮神社の境内からは、奈良・平安期の瓦が出土しており、その後小國社の摂社に置かれていったものと推測される。小國社の奥院(おくのいん)本宮山(ほんぐうさん)を頂点とする天台系の一山組織が確立し、これが遠江国一宮(とおとうみのくにいちのみや)の成立へとつながったのであろう。このほか、霊是(りょうぜ)(大日)山や三倉田能にも山岳密教寺院(さんがくみっきょうじいん)がこのころ再編された。
(1)小國神社楼門と社殿

明治15年消失以前 (小國神社提供写真)
(3)勅使参道

現参道右手に一段高い杉並木が残る。 (森町一宮 小國神社)
図-14 森南部域の荘園・公領推定図

(4)粟倉村絵図

深養父(ふかやぶ)清原氏の館跡と推定される粟倉大城戸遺跡付近の絵図。
(森町円田 個人所蔵文書)
図−15 本宮山を頂点とする寺社関係図

黒四角(■)=神社 黒丸(●)=寺院
遠江国見山(本宮山)の南麓に開かれた遠江国一宮の寺院・神社
(5) 白鬚 ( しらひげ ) 神社

勅使の霊社といわれる小國神社の末社。
(森町円田 大垣内大城戸鎮座)
図−16 平安時代末期の和鏡拓影

(白山神社所蔵)
(6)遠江国の国見岳 ( くにみたけ ) 本宮山

国司が、国内の様子を見わたしたという御山で、一宮の奥院(上宮)が祀られ、三河国にも同様に本宮山がある。
(7)阿弥陀如来坐像

(三倉田能蔵泉寺)
(8)小國神社と対をなす天宮神社

(森町天宮 宮山)
(9)一宮別当寺であった蓮華寺

(森町森 大門)
(10)遠江国一宮小國神社社殿

(森町一宮 宮代)
(11)獅子ヶ鼻と呼ばれる岩室寺の行場

(豊岡村岩室)
(12)奈良期の瓦

(森町天宮 天宮神社出土)
(13)蓮華寺薬師堂古瓦

(森町森 蓮華寺出土)
(14)仁安3年 在銘 ( ざいめい ) 経筒 ( きょうづつ )外容器

(森町一宮 小國神社所蔵)
(15)金剛界大日如来仏頭

(豊岡村敷地 岩室観音堂)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






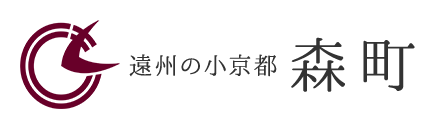

更新日:2019年03月05日