41 交通・信仰
森町を南北に貫いている主要な道路を「秋葉道(あきはみち)」といったり、信州(長野県)へ通じているから「信州街道(しんしゅうかいどう)」といった。また、塩などの生活用品を送っていたから「塩の道(しおのみち)」とも呼ばれていた。山と平野との境を通っている東西の道は、掛川から三ヶ日を経て豊橋に通じている東海道の脇街道である。森町は東西の道と南北の道が交差する重要な地点であった。
町の真ん中を流れている太田川は、下流部の田畑を 潤 ( うるお ) し、上流部のお茶や 椎茸 ( しいたけ ) ボタに湿り気を与え、アユ釣りや水遊びの場にもなっているが、かつては山間部の材木を下流に流したり、森町の商品を河口の福田港へ運ぶ交通路にもなっていた。
この太田川の水源の神として 小國 ( おくに ) 神社 ( じんじゃ ) が祭られた。それは 遠江国 ( とおとうみのくに ) の 一宮 ( いちのみや ) となり、
由緒ある格式の高い神社として古代以来ずっと崇敬(すうけい)されている。曹洞宗の中心的な寺院である大洞院(だいとういん)は、座禅の道場であるが、森の石松の墓があることからわかるように、庶民的な一面をもっていて、正月には餅を焼いて食べると風邪を引かないし、お砂をもらって屋敷にまくと悪いことがおこらないという。
田能(たのう)の蔵泉寺では県指定文化財になっている大般若経で加持(かじ)祈祷(きとう)をして参拝者の健康を祈る。片吹の大日堂には大きな石棒があって子授け、安産祈願をし、黒石の薬師堂では春秋の彼岸の間は鉦(かね)をたたき続けるという風習が続いている。吉川流域の鍛冶島の日月神社(にちげつじんじゃ)は二十人当(にじゅうにんとう)という二十人が交替で神社の祭りを請け負っている宮座(みやざ)の形態を残している。
(1)太田川と高平山

つて太田川は物資を運ぶ大動脈であり、森市場(もりいちば)の繁栄もこうした水運を語らずには理解できない。
(森町飯田 市場橋より)
(2)「遠江国見艸(とおとうみくにみぐさ)」 周智郡之図

山中一円は豊かな資源を持っている。
信州へと続く山並がよくわかる。
(森町円田 個人所蔵)
(3)大日山・ 春埜山 ( はるのさん ) 道標

大河内の峠は霊山への登山の分岐点で、かつては旅館もあった。
(森町三倉 大河内)
(4)大日山の火焼三昧 ( かしょうざんまい )

毎年9月27日に行う柴灯護摩供養で、川根町や浜辺の人たちで賑わう。
(森町三倉 大日山)
(5)春埜山登山道

大河内浜見場から北方に向かって登りかかったところで、かつてはここに黒塗りの大きな鳥居があったという。
(森町三倉 大河内)
(6)遠江本宮山道標

国見岳本宮山を経て光明山や秋葉山に通じる、小國神社の境内にひっそり残る道標。
(森町一宮 小國神社)
(7)本宮山祭

毎年1月6日午前10時から山頂でおこなわれる。小國神社の本宮山奥岩戸神社は毎月6日が縁日である。
(森町薄場 平成10年1月6日)
(8)餅投げ

神事が終わるといよいよ餅投げである。 山の土手から思い切り投げる。
(森町中川下 厳島神社)
(9)大洞院の餅焼き

正月の初詣でには餅を焼いて食するとカゼをひかないという。
(森町橘 大洞院)
(10)大日山の瓜祈祷

毎年7月土用の丑寅の日に行われる。
胡瓜に疫病を付けて土中に埋め込む。
(森町三倉 大日山)
(11)粟倉薬師 寅 ( とら ) 年の御開帳

12年に1度寅の春彼岸におこなわれ、五色糸を指にむすび、これよりサラシを外の塔婆まで伸ばす。
御縁のあるようにと五円玉をこれにつるす。
(森町円田 岳進 平成10年3月21日)
(12)日月神社の粟栽培

特殊神饌(しんせん)粟おこわを捧げるために、毎年当屋(とうや)が責任をもって栽培している。
(森町鍛冶嶋 門田の畑 平成10年9月)
(13)家の中の神々

刀熊(なたくま)は亀久保村の分村で、山の中腹を切り開いた数戸の集落であった。 座敷には多くのお礼をはりつけた神棚が祀られている。
(森町亀久保 刀熊)
(14)石川の地蔵さま

毎年8月23日の夜、ろうそく1本のついている間だけお扉が開かれる。
うらぼんの地蔵信仰がこの村の大きな意味を持つ。
(森町中川下 地蔵寺)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






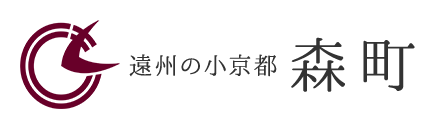

更新日:2019年03月05日