森町の由来
町の名前の由来
森町という名前の村ができたのは、鎌倉時代中頃です。 森町は、別名「三木の里」といわれています。「森」という字が三つの木から成っているためです。町は太田川を中心に三方を山に囲まれているため、「森町」という名前は町という字まで入れて一つの固有名詞になっています。森町の名前は、昔から変わらない美しい町の自然をそのまま文字にしたすばらしい名前です。
森町の歴史のあらまし
太田川の豊かな流れに育まれた森町の歴史は古く、流域の丘陵部には縄文時代の遺跡の分布が認められています。弥生時代になると集落が形成され、人々の生活の基盤も、それまでの狩猟・採集から稲作へと変わり、生産力も飛躍的に増大しました。金属器が作られるようになったのもこの頃のことです。6世紀中頃から7世紀前半にかけては、 谷口(やぐち) ・ 観音堂横穴群(かんのんどうおうけつぐん) などが形成されました。
この地方が「遠江国」と呼ばれるようになった奈良時代から平安時代にかけて、十二段舞楽で名高い 小國 ( おくに ) 神社と 天宮 ( あめのみや ) 神社が創建されました。 山名 ( やまな ) 神社に伝わる天王祭舞楽とあわせ、今日まで伝えられている3つの舞楽は国の重要無形民俗文化財に指定されています。
室町時代に入り、遠江には 斯波 ( しば ) 氏・今川氏が 覇 ( は ) を競いますが、永正年代には今川氏の制するところとなります。しかし、 桶狭間 ( おけはざま ) での敗戦をきっかけに今川氏は急速に衰え、ついに武田・徳川両軍のため滅亡してしまいます。その後、森町付近では両軍の激しい攻防が繰り返されますが、結局は徳川家康の支配下に入ることになります。天方城をはじめ町内に残るいくつかの山城は、つわものどもの夢の跡を今に伝えています。
江戸時代中期、「火伏せの神」として秋葉山信仰が盛んで、森町は街道の宿場町としてとても栄えました。そのため、いまでも立派な常夜灯が、北戸綿や城下、黒石などに残っています。また、森町は古着の町でも有名でした。当時は全国の古着市場の相場を左右したといわれるほどです。このようなことから、葛飾北斎の「栄える都市の番付」に名があげられるほどで、まちの中心部の路地には、栄えた頃の面影が残っています。
町村制施行前の森町
森町の江戸時代は、ほとんどが旗本領でしたが、明治になって全部が静岡藩に変わりました。その後、明治4年には、廃藩置県で浜松県、明治9年には、今の静岡県になりました。今の森町は、もと周智郡山名庄の中の飯田郷、園田郷、 衾ノ谷(ふすまのや) 郷、太田郷、天宮郷、天方郷、そして豊田郡三倉郷の7郷からできていて、7郷は明治22年の市制町村制施行で6つの新町村名に変わりました。
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






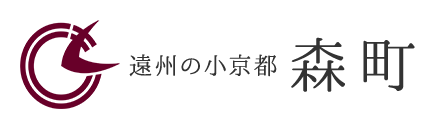

更新日:2024年08月29日