45 森町の神社建築
宗教法人として登録された神社は町内に40社程あり、天宮神社本殿と拝殿の2棟が県の文化財に指定されている。一方、小國神社本殿と三嶋神社本殿は町指定となっている。
森町の神社建築の遺構は、ほとんどが江戸時代以降のものである。それらの中で、江戸中期頃までに建立された比較的古い社殿は、表の如(ごと)くである。ただし、三倉大久保の八幡神社本殿は1684年(貞享元年)の造営として考えられるが、その前の1552年(天文21年)の本殿の部材を再び使用したか、あるいは忠実に以前の意匠を 踏襲(とうしゅう)したとみられ、室町時代の趣を残した 好例(こうれい)である。
町内では、本殿が覆い屋の中に納められていることが多い。したがって本殿の規模は小さく、見世棚(みせだな)形式をとる例も見られる。 社殿形式については、ここ森町においても全国的な傾向と同じく、前方の屋根を長く葺(ふ)き降ろした流造(ながれづくり)の本殿が最も多い。
流造以外の例として、鍛冶島の日月神社本殿は外側に棟持ち柱を立てた 神明造(しんめいづくり)の形式を見せている。
一宮の小國神社は出雲大社の 大国主命(おおくにぬしのみこと)を祭神として創始していることから、本殿の形式も大社造となっている。
宮代の神明宮本殿は切妻屋根で棟持ち柱を有するが、前流れの屋根は幅が狭められて向拝の屋根となり、神明造・流造・向拝(こうはい)庇付(こうはいひさしつ)き切妻造(きりづまづくり)などが折衷された珍しい形式である。
表−18 神社社殿建立年代一覧表
| 番号 | 年代 | 建物名 (所在地) |
構造形式 | 典拠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寛文12年(1671年) | 三島神社本殿 (森) |
三間社、流造、銅板葺 | 棟札(むなふだ) |
| 2 | 貞享(じょうきょう)元年(1684年) | 八幡神社本殿 (大久保) |
一間社、流造、板葺 | 棟札 |
| 3 | 元禄10年(1697年) | 天宮神社本殿 (森) |
三間社、流造、檜皮葺 | 棟札 |
| 4 | 元禄10年(1697年) | 天宮神社拝殿 (森) |
入母屋造、桟瓦葺、妻入り | 社伝(しゃでん) |
| 5 | 享保8年(1723年) | 金山神社本殿 (草ヶ谷) |
一間社、流造(見世棚)、柿(こけら)葺 | 棟札 |
| 6 | 享保12年(1727年) | 八幡神社本殿 (大鳥居) |
一間社、流造、檜皮葺 | 棟札 |
| 7 | 享保17年(1732年) | 山名神社本殿 (飯田) |
三間社、流造、銅板葺(旧檜皮葺) | 棟札 |
(1)天宮神社本殿

1697年(元禄10年)造営の簡素な造りである。(森町天宮)
(2)天宮神社拝殿

本殿と同時に造営されたものであるが、その後、屋根は桧皮(ひわだ)から桟瓦(さんがわら)に、柱や縁も新しい部材に替わった。(森町天宮)
(3)小國神社本殿

1886年(明治19年)11月に官費をもって完成。(森町一宮)
(4)八幡宮本殿

屋根は大和葺という古様式を用い、全体に丹を塗り、扉の上部には宝珠(ほうじゅ)と霊芝を描く、遠州では、残存する社殿としては最も古い部類に属する。 (森町三倉 大久保)
(5)三嶋神社本殿虹梁

三嶋神社は1661年(万治4年)正月に焼失し、1672年(寛文12年)に完成した。 この虹梁は当時の意匠を残す彫刻である。 (森町森)
(6)金山神社本殿

見世棚(みせだな)造りの柿(こけら)葺きのもので、棟札によれば1723(享保18)年の葺替えとみえ、そのほかの意匠からもこの時代の建造と判断することができる。 (森町草ヶ谷)
(7)山名神社本殿

1732年(享保17年)9月の棟札によれば、市場の大工鈴木安右衛門・伝四郎らによって造営された。(森町飯田)
(8)小國神社神饌殿

本殿と同様に1886年(明治19年)9月25日に再建されたものであるが、平成9年に老朽化のため解体された。この写真は平成8年に撮影したものである。(森町一宮)
(9)大鳥居八幡宮本殿

1727年(享保12年)に建立した本殿で、重厚な造りである。 (森町大鳥居)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
社会教育課 文化振興係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森92-1
電話番号:0538-85-1114
メールでのお問い合わせはこちら






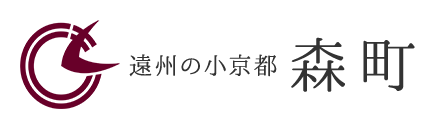

更新日:2019年03月05日