児童手当制度が変わります
令和6年12月支給分(令和6年10月分)から、児童手当制度の一部が変わります。
児童手当法の改正内容
児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)されました。主な改正点は次のとおりです。
1 所得制限の撤廃
2 支給期間が高校生年代※までに
3 第3子以降の児童の支給額が月額30,000円に
4 支払月が年6回(偶数月)に
5 第3子加算の算定対象が大学生年代※までの子に拡充
※詳細は「第3子加算のカウント方法」をご確認ください。
| 改正前 | 改正後(令和6年10月~) | |||
| 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 |
|
| 3歳~小学校修了 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 |
10,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
| 所得制限 |
あり |
なし 特例給付は廃止 |
||
| 支給回数 | 年3回(2・6・10月)支払 | 年6回(偶数月)支払 | ||
・改正後の最初の支給は令和6年12月10日となります。
・令和6年10月支給分(6月~9月分)は、改正前の支給額で支給します。
・公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。申請が必要かどうかは、勤務先にご確認ください。
※高校生年代:中学生修了後、18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで
※大学生年代:高校生年代終了後、22歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで
第3子加算のカウント方法
☆児童手当の受給者が、生活費・食費等を負担している22歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの子のうち、年長者から第1子、第2子とカウントします。
※仕事やアルバイトで収入を得ており、経済的に自立している・受給者から養育されていない場合はカウント対象外となります。
養育している:子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態のこと。
例:19歳(大学生)、16歳、12歳、7歳の4人の子を養育している場合。

申請について
制度改正に伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は手続きが必要です。
☆ご注意
・令和6年10月1日時点の見込に基づく内容で申請してください。
・外国籍の方は家族全員の在留カード、振込口座(銀行名・支店名・口座番号・名義)が分かるものをお持ちください。(郵送の場合は写しを同封してください。)
☆手続きフローチャートを参考にご覧ください

Aに該当する方
高校生年代の児童のみを養育している方・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方等
対象児童の住民票が森町にあり、申請が必要と思われる場合は申請案内を送付しています。
※児童と別居している場合や、森町での申請履歴がない場合は案内が送付されません。ご自身で、申請が必要かどうかご確認をお願いいたします。
【手続きに必要なもの】
・児童手当認定請求書(PDFファイル:336.7KB)
・児童手当認定請求書(記入例)(JPEG:638.6KB)
・請求者名義の口座情報(金融機関・店番・口座番号・名義)が分かるもの
・請求者の健康保険証の写し
(3歳未満の児童を養育しており、私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員共済等に加入している方のみ。)
※請求者は、父母等の2人以上で同一の児童を養育し、生計が同一の場合、父母のうち所得が高い方となります。
<その他、場合によって必要となる書類>
請求者の配偶者、児童の住民票が町外にある場合
・配偶者、児童のマイナンバーが確認できるもの
(マイナンバーカード、マイナンバー付きの住民票の写し等)
請求者と高校生年代の児童が別居している場合
・別居監護申立書(PDFファイル:59.2KB)
「請求者が生計費を負担している大学生年代の子」を含めた子の合計人数が3人以上の場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92.2KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(JPEG:671.5KB)
離婚、離婚協議中で父母が別居しており、父母のうち、児童と同居している方が認定請求する場合
・同居父母優先申立書
・離婚協議中で有ることが客観的に確認できる書類
(離婚協議内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調定不成立証明書など)
Bに該当する方
現在、児童手当を受給していて、森町で児童手当を受給したことがない高校生年代の児童を養育している方等
【手続きに必要なもの】
・額改定認定請求書(PDFファイル:173.3KB)
・額改定認定請求書(記入例)(JPEG:527.4KB)
<その他、場合により必要となる書類>
請求者の配偶者、児童の住民票が町外にある場合
・配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバー付きの住民票の写し等)
Cに該当する方
現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉(大学生年代)を含むと、養育している児童が3人以上となる場合
【手続きに必要なもの】
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92.2KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(JPEG:671.5KB)
※本来、「児童手当額改定認定請求書」も提出が必要ですが、制度改正の経過措置として令和7年3月31日までに手続きされた場合はこれを省略できます。
※「確認書」に記載された子が就学していない場合、毎年6月に現況届の提出が必要になります。また、「確認書」に記載された子が卒業した場合、引き続き児童手当の第3子加算の対象とするには、再度「確認書」の提出が必要となります。
※兄姉が就職している等で独立して生計を立てている場合(自分で健康保険に加入している等。)は、第3子加算の対象にはなりませんので「確認書」の提出は不要です。
<その他、場合によって必要となる書類>
請求者の配偶者、児童の住民票が町外にある場合
・配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード、マイナンバー付きの住民票の写し等)
制度改正による申請が不要な方
以下に該当する方は、原則として申請は不要です。
・児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方
・児童手当を受給中で、第3子加算に該当しており、加算額の増額により手当額が増額となる方
・児童手当を受給中で、区分が「特例給付」であるため、所得制限廃止により手当額が増額となる方
・児童手当を受給中で、森町で児童手当を受給したことがある高校生年代の児童が支給対象となるため、手当額が増額となる方
※高校生年代の児童と別居している方は、申請が必要な場合があります。
受付期間
令和6年8月1日(木曜日)から9月30日(月曜日)まで【必着】
※提出が遅れると支給月も遅れます。
なお、改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日までに(必着)です。
令和7年4月1日以降の申請となる場合は、令和6年10月分にさかのぼっての支給はできません。(申請した月の翌月からの支給となります。)
※令和6年9月30日より前に森町から転出する場合は、転出先の自治体で手続きをおこなってください。
提出先
※郵便でのご提出にご協力をお願いいたします。
〒437-0215
森町森50番地の1 森町保健福祉センター
健康こども課こども家庭係 宛
※窓口の場合
森町保健福祉センター1階 こども家庭係窓口
受付時間:8時30分~17時15分 ※土日祝は受付不可
書類ダウンロード
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
健康こども課 こども家庭係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6330
メールでのお問い合わせはこちら






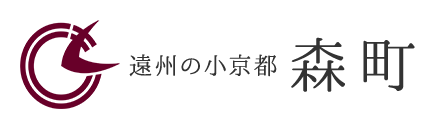

更新日:2024年07月16日